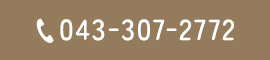腹部膨満感とは
 腹部膨満感はお腹が張って苦しい状態を指します。
腹部膨満感はお腹が張って苦しい状態を指します。
食事中に一緒に飲み込んだ空気や消化管内で発生したガスは呼気やおならとして排泄されます。この消化管内のガスの産生と排泄のバランスが崩れ、ガスが過剰に溜まることで腹部膨満感が起こります。ストレスや自律神経の乱れ、腸内環境の悪化などにより過剰なガスが発生します。便秘や過敏性腸症候群による消化管運動の低下や腸閉塞によりガスの排泄が低下します。
このように、ガスが発生して起こる場合と、胃腸の運動が低下して起こる場合があります。
膨満感が気になる方は、軽度な症状でもお気軽にご相談ください。
腹部膨満感を伴う疾患
便秘
便秘は、腸内に便がたまるので腹部膨満感を生じることがよくあります。便秘が長引くと、痔や大腸疾患を引き起こす可能性があるため、適切な排便コントロールが重要です。
腸閉塞
腸閉塞は、腸の血流障害や腫瘍、腸管癒着、蠕動運動の低下などが原因で、腸の内容物が通過できない状態を指します。腹部膨満感に加え、強い腹痛や嘔吐を伴います。早期の診断と治療が必要です。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、ストレスが引き金となって発症することが多い疾患です。腸機能の不全や知覚過敏が原因で、器質的な病変は見られませんが、腹痛や膨満感、便秘、下痢などの症状が長期間続くことがあります。
呑気症
呑気症は、大量の空気を飲み込むことで胃腸に空気がたまり、腹部膨満感や腹痛を感じたり、げっぷやおならが増えたりする疾患です。
症状の軽減には、空気を飲み込まないよう早食いを避けたり、炭酸飲料を控えるといった生活習慣の見直しやストレスの軽減が必要です。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を起こす状態です。食生活の欧米化により、広い年齢層で罹患が増加しています。症状としては、呑酸、胸焼け、咳とともに、腹部膨満感も現れることがあります。
急性胃腸炎
急性胃腸炎では、胃腸の粘膜に炎症が起こることで腸管が浮腫み、腸液が停滞して腹部膨満感が現れることがあります。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは、胃の粘膜に病変がないにもかかわらず、膨満感、胃もたれ、胃の不快感、みぞおちの痛みなどの症状が現れる疾患です。病変がないことを確認するため胃カメラ検査が必要です。
腹部腫瘍
胃がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣腫瘍などの腫瘍ができると、腫瘍による圧迫で膨満感が生じることがあります。早期の診断と治療が大切です。
上腸間膜動脈症候群
上腸間膜動脈症候群は、急激な体重減少や脂肪の減少により、十二指腸が血管に圧迫されて通過障害が起こり、膨満感や胃もたれ、腹痛などの症状が現れる疾患です。食後に仰向けになると症状が悪化し、腹ばいや四つん這いの姿勢になると軽減します。
腹部膨満感の検査
症状、発症時期、持続時間などを詳しく問診し、触診によって膨満感の部位を確認します。腹部レントゲン検査、腹部超音波検査でガスのたまり具合や内臓の状態をチェックします。胃カメラ検査や大腸カメラ検査は、粘膜を直接観察できるため病変の有無を確認するため有用な検査です。
腹部膨満感の治療
 腹部膨満感の治療は、その原因によって異なります。疾患が原因である場合は、その治療を行い、心身のストレスや食事習慣が影響している場合には、生活習慣の改善に努めることが必要です。必要に応じて、薬物療法を行うこともあります。
腹部膨満感の治療は、その原因によって異なります。疾患が原因である場合は、その治療を行い、心身のストレスや食事習慣が影響している場合には、生活習慣の改善に努めることが必要です。必要に応じて、薬物療法を行うこともあります。